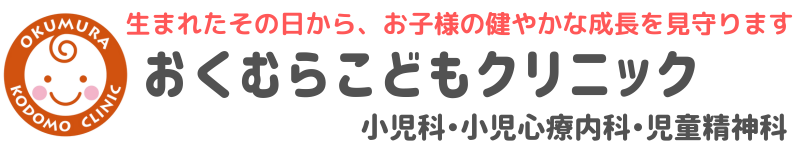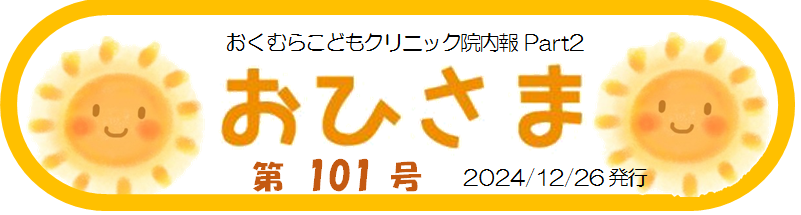おひさま 第101号~5歳児健診が・・・/お子さんと会話していますか? ~
かさい先生のお話【5歳児健診が・・・】
国は5歳児健診を積極的におこなっていく方針を出しました。
発達が気になるお子さんを外来で診察している小児科医からするとやっと本腰を入れてくれるようになってきたのかなという感じです。小児科では以前より、「はっきりと異常というわけではないけれど、ちょっと気になる子どもたち」がいました。たとえば落ち着きがない、指示が入りにくい、一人遊びが多い、集団行動が苦手、癇癪を起こす、興味に偏りがある、体の動きがぎこちないなどが気になる子どもたちの存在があります。そのような子どもたちの中に発達障がいの特性をもったお子さんがやはり多くみられます。そのため近年5歳児健診の重要性がずっと言われていましたが、残念ながら他の定期健診に比べて認知度が低いままでした。
今までの、1か月・4か月・10か月・1歳6か月・3歳児の健診は、発育、胸腹部の聴診や触診、言葉や発達面をチェックします。一方5歳児健診はおもに発達、行動、運動面のチェックになります。お子さんを把握するために、会話や指示に従う様子など情緒行動面、体幹支持や手指の巧緻性(こうち)などの運動面を診察する必要があります。当院でおこなっていた個別での5歳児健診は他の健診にくらべ、診察には時間をかけてやっていました。また、5歳児健診での気づきから、お子さんへの適切な対応や、就学へ向けての準備をし、学校生活がすごしやすい環境を整えてあげることにつながっていくことが期待されています。
5歳児健診をおこなっていて、目に見えて最もわかりやすい点は、運動面の様子だと自身は考えています。イスに姿勢良く座っていられるか、片足立ちやケンケンがバランスよくできているか、じゃんけんの時のリズム感などが比較的わかりやすいと思います。発達の特性を持ったお子さんは発達性協調運動障がいと言われる運動面に問題を持っているお子さんが多くおられます。就学をすれば1時限45分程度、4-5コマ姿勢保持をすることを求められます。運動面に問題があると就学してから、長時間座っていられない、姿勢が崩れて授業に集中できない、左右の協調運動が苦手で筆記や定規の使用に支障をきたすなどの症状は学習面に大きく影響します。健診の時に運動面に気になる様子があれば、できるだけ身体づくりを頑張ってくださいとアドバイスしています。
発達が気になるお子さんを外来で診察している小児科医からするとやっと本腰を入れてくれるようになってきたのかなという感じです。小児科では以前より、「はっきりと異常というわけではないけれど、ちょっと気になる子どもたち」がいました。たとえば落ち着きがない、指示が入りにくい、一人遊びが多い、集団行動が苦手、癇癪を起こす、興味に偏りがある、体の動きがぎこちないなどが気になる子どもたちの存在があります。そのような子どもたちの中に発達障がいの特性をもったお子さんがやはり多くみられます。そのため近年5歳児健診の重要性がずっと言われていましたが、残念ながら他の定期健診に比べて認知度が低いままでした。
今までの、1か月・4か月・10か月・1歳6か月・3歳児の健診は、発育、胸腹部の聴診や触診、言葉や発達面をチェックします。一方5歳児健診はおもに発達、行動、運動面のチェックになります。お子さんを把握するために、会話や指示に従う様子など情緒行動面、体幹支持や手指の巧緻性(こうち)などの運動面を診察する必要があります。当院でおこなっていた個別での5歳児健診は他の健診にくらべ、診察には時間をかけてやっていました。また、5歳児健診での気づきから、お子さんへの適切な対応や、就学へ向けての準備をし、学校生活がすごしやすい環境を整えてあげることにつながっていくことが期待されています。
5歳児健診をおこなっていて、目に見えて最もわかりやすい点は、運動面の様子だと自身は考えています。イスに姿勢良く座っていられるか、片足立ちやケンケンがバランスよくできているか、じゃんけんの時のリズム感などが比較的わかりやすいと思います。発達の特性を持ったお子さんは発達性協調運動障がいと言われる運動面に問題を持っているお子さんが多くおられます。就学をすれば1時限45分程度、4-5コマ姿勢保持をすることを求められます。運動面に問題があると就学してから、長時間座っていられない、姿勢が崩れて授業に集中できない、左右の協調運動が苦手で筆記や定規の使用に支障をきたすなどの症状は学習面に大きく影響します。健診の時に運動面に気になる様子があれば、できるだけ身体づくりを頑張ってくださいとアドバイスしています。
スタッフコラム【お子さんと会話していますか?】
年末から年始にかけてのお休みはご家族でお出掛けまたは自宅でのんびり過ごされることと思います。
日頃なかなか忙しくてお子さんにゆっくりと向きあえないという親御さん、この機会にたくさん会話できると良いですね。
日頃なかなか忙しくてお子さんにゆっくりと向きあえないという親御さん、この機会にたくさん会話できると良いですね。
子どもの語彙力・想像力を育てよう
幼少期は言葉に出せるまである程度時間がかかりますが、成長と共に言葉を覚えていきます。自分の気持ちを表現するのに大切なのが語彙力ですが、多ければ多いほど自分の気持ちを表現しやすくなります。語彙力はある日突然増えるものではなく、子どもたちは赤ちゃんの頃から会話を吸収しているのです。
一緒に歌う、ことば遊びをするなど口を鍛える遊びはもちろんのこと、本を読むことや読み聞かせでことばの言い回しなどたくさん学ぶことができます。そして手を使って作るものは言葉でなくても表現することができます。ブロック、パズル、工作、折り紙、絵画などこうしたらこうなると考えながら作る想像力を育てます。
一緒に歌う、ことば遊びをするなど口を鍛える遊びはもちろんのこと、本を読むことや読み聞かせでことばの言い回しなどたくさん学ぶことができます。そして手を使って作るものは言葉でなくても表現することができます。ブロック、パズル、工作、折り紙、絵画などこうしたらこうなると考えながら作る想像力を育てます。
子どもに体験をさせよう
テレビを観て、話を聞いて知っているのと、やったことがあるのとでは情報量が大きく異なります。私たち大人でもあることですが、ただ単に見たこととは記憶に残りにくく、自分が体験したことは何年経ってもその記憶が残ります。子どもと旅行に行く時は必ず体験を入れるというご家族もあるくらい、子どもに経験させることは大切です。体験が自信になり、子ども自身の会話力にもつながっていきます。
話しやすい環境をつくろう
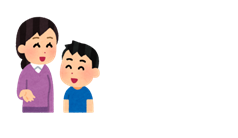
会話のなかで大切なのは、子どもの声を受け入れてまずは共感することです。子どもは自分の気持ちを受け止めてもらえると安心して自分を表現するようになるでしょう。誰でも聞いてもらいたいことを勇気を出して言った時、共感してもらえると嬉しいですし、この人ならもっと話したいという気持ちになります。
子どもが話してくれないのは、もしかしたら親御さんが無意識のうちに共感ではなく否定から入っているからかもしれません。
今や両親共働き家庭が増えて、子どもと話す時間が多いとは言えないなか、学校や園であったこと体験したこと、友達の様子などなんでもいいです、親御さんは聞き上手になって会話をひきだしてあげるといいですね。
子どもが話してくれないのは、もしかしたら親御さんが無意識のうちに共感ではなく否定から入っているからかもしれません。
今や両親共働き家庭が増えて、子どもと話す時間が多いとは言えないなか、学校や園であったこと体験したこと、友達の様子などなんでもいいです、親御さんは聞き上手になって会話をひきだしてあげるといいですね。