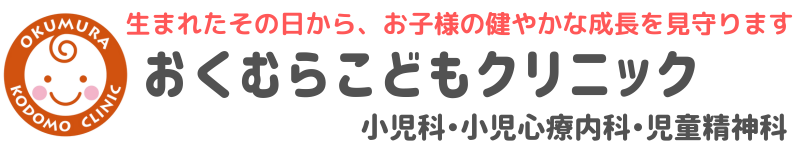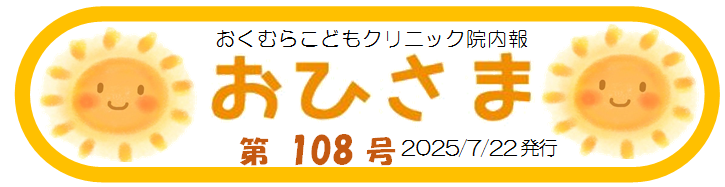おひさま 第108号~ADHDに関する書籍を読んでみて/子どもの留守番~
かさい先生のお話【ADHDに関する書籍を読んでみて】
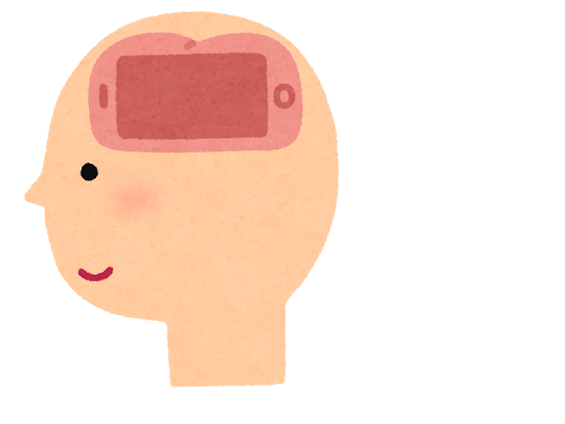
2020年にスウェーデンの精神科医アンデシュ・ハンセン先生の「スマホ脳」という書籍が大変話題になりました。家庭でゲームやスマホに悩まれている親御さんはぜひ読んでおきたい一冊です。その後もハンセン先生は「最強脳」、「運動脳」、「ストレス脳」、「メンタル脳」と複数の書籍を出されておりどれも興味深く読ませていただきました。訳本ですがどれも読みやすく興味深い内容の書籍でした。
更に最近出版された「多動脳-ADHDの真実」、発達障がいのADHDに関しての書籍です。クリニックで発達とこころの外来を担当している自身としては大変興味深く読ませていただきました。ADHDの特徴を持つお子さんの親御さんには是非とも読んでいただきたい内容の書籍でした。
ADHDの特性を持っているお子さんの親御さんは、お子さんのネガティブな特徴を主訴に来院されます。「落ち着きがない」「じっとしていない」「勉強に集中出来ない」「忘れもの、なくしものが多い」「後片付けできない」などなど・・・。このようなネガティブな特徴は現代の生活においては残念ながら弱点になってしまいます。しかしそのような弱点を持ったADHDの特性を持ったお子さんたちにも、一般的な発達(定型発達)のお子さんたちが持っていない強みの能力が存在しています。まずは発想力が非常に豊かで、様々な斬新なアイデアがたくさん出やすい特徴を持っています。クリエイティブな職業に向いているとも言われます。また興味を持ったことに対しては人並み以上の高い集中力(ハイパーフォーカス)を発揮することが出来ます。けど、興味のないことは一向にしませんが・・・。また定型発達の方がピンチで緊張してしまい本来の能力が発揮できないことが多いのに比べ、ADHDの特徴を持ったお子さんはピンチでも意外に冷静で集中力を発揮して持っている能力を発揮しやすいことが書いてありました。確かにクリニックで多くの子どもたちを診てきましたが、今のところなぜか高校受験で失敗したお子さんは一人もいません。切羽詰まったときに持っている能力を発揮出来るお子さんが多いのも納得しました。またADHDのお薬のメリット、デメリットのことや、ADHDのお子さんにとって運動が極めて大切であることが書いてありました。ADHDのお子さんのネガティブな面だけでなく、強みを伸ばしていくことが非常に大切であると勉強させていただいた一冊でした。
更に最近出版された「多動脳-ADHDの真実」、発達障がいのADHDに関しての書籍です。クリニックで発達とこころの外来を担当している自身としては大変興味深く読ませていただきました。ADHDの特徴を持つお子さんの親御さんには是非とも読んでいただきたい内容の書籍でした。
ADHDの特性を持っているお子さんの親御さんは、お子さんのネガティブな特徴を主訴に来院されます。「落ち着きがない」「じっとしていない」「勉強に集中出来ない」「忘れもの、なくしものが多い」「後片付けできない」などなど・・・。このようなネガティブな特徴は現代の生活においては残念ながら弱点になってしまいます。しかしそのような弱点を持ったADHDの特性を持ったお子さんたちにも、一般的な発達(定型発達)のお子さんたちが持っていない強みの能力が存在しています。まずは発想力が非常に豊かで、様々な斬新なアイデアがたくさん出やすい特徴を持っています。クリエイティブな職業に向いているとも言われます。また興味を持ったことに対しては人並み以上の高い集中力(ハイパーフォーカス)を発揮することが出来ます。けど、興味のないことは一向にしませんが・・・。また定型発達の方がピンチで緊張してしまい本来の能力が発揮できないことが多いのに比べ、ADHDの特徴を持ったお子さんはピンチでも意外に冷静で集中力を発揮して持っている能力を発揮しやすいことが書いてありました。確かにクリニックで多くの子どもたちを診てきましたが、今のところなぜか高校受験で失敗したお子さんは一人もいません。切羽詰まったときに持っている能力を発揮出来るお子さんが多いのも納得しました。またADHDのお薬のメリット、デメリットのことや、ADHDのお子さんにとって運動が極めて大切であることが書いてありました。ADHDのお子さんのネガティブな面だけでなく、強みを伸ばしていくことが非常に大切であると勉強させていただいた一冊でした。
スタッフコラム【子どもの留守番】
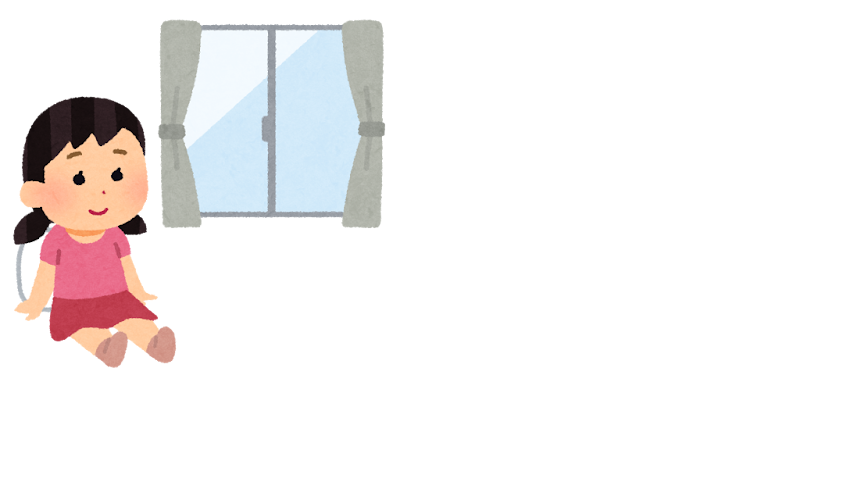
皆さんは子どもだけで留守番をさせていますか?
子どもだけでの留守番は、規則正しく過ごしているか、また万が一のことが起こっていないか心配が尽きません。特に夏休みは普段よりも子どもだけで留守番をする機会が多いのではないでしょうか。共働きで、どうしても親族、学童などに預けることができず、子どもだけで留守番をせざるを得ない方は少なくありません。危険なリスクがあること、気をつけることを家族で話あうと良いでしょう。
子どもだけでの留守番は、規則正しく過ごしているか、また万が一のことが起こっていないか心配が尽きません。特に夏休みは普段よりも子どもだけで留守番をする機会が多いのではないでしょうか。共働きで、どうしても親族、学童などに預けることができず、子どもだけで留守番をせざるを得ない方は少なくありません。危険なリスクがあること、気をつけることを家族で話あうと良いでしょう。
◇火・水の事故リスク◇

キッチンでの火の事故や、お風呂場での水の事故に対する備えが大切です。
子どもの年齢によっては、火や水の怖さを十分理解できません。不注意やいたずらから事故を起こす危険性も考えられ、一歩間違えると大きな事態にもつながります。火の元栓は閉めておく、お風呂の水は抜いておく、またはお風呂の鍵をかけておくなど対策をしましょう。
子どもの年齢によっては、火や水の怖さを十分理解できません。不注意やいたずらから事故を起こす危険性も考えられ、一歩間違えると大きな事態にもつながります。火の元栓は閉めておく、お風呂の水は抜いておく、またはお風呂の鍵をかけておくなど対策をしましょう。
◇犯罪に巻き込まれるリスク◇

不審者はさまざまな方法で家の中に侵入してきます。子どもだけで留守番をしているときに泥棒に入られる可能性もゼロではありません。玄関扉のドアチェーン、二重ロックなどをして、しっかり施錠をすることが需要です。インターホンがなってもインターホンに出ない、鍵や扉を開けないようにと各家庭でルールを決めると良いでしょう。
◇転落事故リスク◇

子どもがベランダから転落する事故も少なくありません。きちんと鍵をかけ、立ち入らせないようにすることです。プランターやコンテナボックスなど足場になりそうな物があれば、手すりから遠ざけるなど対策をしましょう。
★子どもからの連絡手段を決めておく
事故が起こったり急な体調不良の時の為に、子どもとの連絡手段を決めておけば、お互いに安心して過ごせます。
スマートフォン、固定電話で連絡をとったり、見守りカメラで通話ができるものもあるので心配であれば設置するのも良いでしょう。
子どもは様々な事が出来るようになり、これぐらい大丈夫だろうと思っていてもいつどんな事故が起きるか分かりません。親がいるときはOKでも留守番の時の禁止事項は、子どもが理解できるまで時間をかけて話し合いましょう。
スマートフォン、固定電話で連絡をとったり、見守りカメラで通話ができるものもあるので心配であれば設置するのも良いでしょう。
子どもは様々な事が出来るようになり、これぐらい大丈夫だろうと思っていてもいつどんな事故が起きるか分かりません。親がいるときはOKでも留守番の時の禁止事項は、子どもが理解できるまで時間をかけて話し合いましょう。