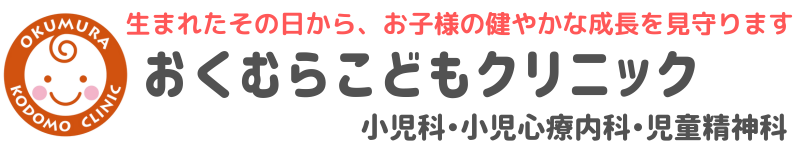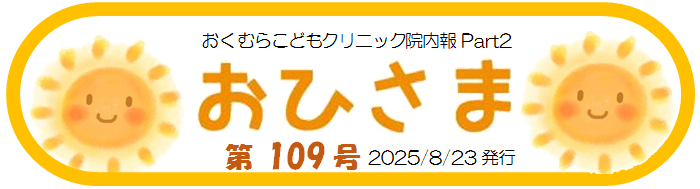おひさま 第109号~ちょっと早いですがインフルエンザワクチンの話/災害への備えはできていますか?~
おくむら先生のお話【ちょっと早いですがインフルエンザワクチンの話】

まだまだ暑い日が続きますが、今月はインフルエンザワクチンのお話です。
毎年10月になるとインフルエンザワクチンの接種が始まります。これまでは注射のインフルエンザワクチン一択でしたが、昨年度から2歳以上19歳未満の方は「フルミスト」というワクチンが選択できるようになりました。
これまで使用されていた注射のインフルエンザワクチンは不活化ワクチンで、12歳以下のお子様は2回接種が必要でしたが、フルミストは生ワクチンで、1回の接種ですみます。また点鼻型といって、針を刺す必要はなく、左右の鼻の穴に1プッシュずつ、ワクチンを投与したらおしまいです。効果は注射のワクチンと同等です。副作用は14日以内に発熱、咳嗽、鼻汁などの症状が出る方が若干みえるようです。注射で痛い思いをせず、1回で終わる点では注射よりよさそうに思えます。
一方気になる点をあげてみると、生ワクチンなので、免疫不全など免疫機能に異常のある疾患を有する方、免疫抑制剤やステロイドなど、免疫抑制をきたす治療を受けている方は接種できません。あと、個人的には鼻水がたくさんでている時にさしても効果があるのかしら・・・と思っています。また生ワクチンで、鼻にさすので、接種してからまもない時期に発熱した場合、インフルエンザの検査をすると、陽性にでてしまいます。ワクチンで陽性なのか、実際にインフルエンザに感染しているのか、判定が難しくなります。さらに抗インフルエンザ薬を使用すると、ワクチン株にも効いてしまい、ワクチンの効果が弱まる可能性もあります。
費用的には、注射の不活化ワクチンより若干高めです。岐阜市のお子様の場合、市の補助が使えますので、例年通りであれば少しお安く接種できるはずです。
みなさんはどちらを選択されますか?当院でも今年度からフルミストの接種を始めます。近くなったらHP等でお知らせしますので、選択肢の一つとして考えてみてください。
毎年10月になるとインフルエンザワクチンの接種が始まります。これまでは注射のインフルエンザワクチン一択でしたが、昨年度から2歳以上19歳未満の方は「フルミスト」というワクチンが選択できるようになりました。
これまで使用されていた注射のインフルエンザワクチンは不活化ワクチンで、12歳以下のお子様は2回接種が必要でしたが、フルミストは生ワクチンで、1回の接種ですみます。また点鼻型といって、針を刺す必要はなく、左右の鼻の穴に1プッシュずつ、ワクチンを投与したらおしまいです。効果は注射のワクチンと同等です。副作用は14日以内に発熱、咳嗽、鼻汁などの症状が出る方が若干みえるようです。注射で痛い思いをせず、1回で終わる点では注射よりよさそうに思えます。
一方気になる点をあげてみると、生ワクチンなので、免疫不全など免疫機能に異常のある疾患を有する方、免疫抑制剤やステロイドなど、免疫抑制をきたす治療を受けている方は接種できません。あと、個人的には鼻水がたくさんでている時にさしても効果があるのかしら・・・と思っています。また生ワクチンで、鼻にさすので、接種してからまもない時期に発熱した場合、インフルエンザの検査をすると、陽性にでてしまいます。ワクチンで陽性なのか、実際にインフルエンザに感染しているのか、判定が難しくなります。さらに抗インフルエンザ薬を使用すると、ワクチン株にも効いてしまい、ワクチンの効果が弱まる可能性もあります。
費用的には、注射の不活化ワクチンより若干高めです。岐阜市のお子様の場合、市の補助が使えますので、例年通りであれば少しお安く接種できるはずです。
みなさんはどちらを選択されますか?当院でも今年度からフルミストの接種を始めます。近くなったらHP等でお知らせしますので、選択肢の一つとして考えてみてください。
スタッフコラム【災害への備えはできていますか?】
9月1日は防災の日とみなさんご存知だと思いますが、1923年9月1日に発生した関東大震災を教訓に、災害への意識を高め、備えを促すために制定されました。
災害に備えて防災グッズ・避難グッズの準備はしていますか?準備ができている人も、以前準備をしてから定期的に見直していますか?準備ができていても年月が経って使えなくなっている可能性もあるため定期的に見直しをすることも大切です。
災害に備えて防災グッズ・避難グッズの準備はしていますか?準備ができている人も、以前準備をしてから定期的に見直していますか?準備ができていても年月が経って使えなくなっている可能性もあるため定期的に見直しをすることも大切です。

お子さんのいる家庭で準備するといいもの

●おむつ、お尻ふき
●ウエットティッシュ
●液体ミルク、粉ミルク、哺乳瓶
●離乳食や保存の効く食べ物
●紙コップ
●バスタオル
●家族の写真と連絡先
●使い捨て手袋
●レジャーシート
●おもちゃ
●保険証と医療受給者証のコピー、母子手帳のコピー
●ウエットティッシュ
●液体ミルク、粉ミルク、哺乳瓶
●離乳食や保存の効く食べ物
●紙コップ
●バスタオル
●家族の写真と連絡先
●使い捨て手袋
●レジャーシート
●おもちゃ
●保険証と医療受給者証のコピー、母子手帳のコピー
水や食料品など基本的な備えに加えて、お子さんのいる家庭ではおむつやミルク、離乳食や保存の効く食べ物は何日分かをまとめて用意するようにしましょう。定期的におむつのサイズや賞味期限を確認し適切なものを準備しておくことも重要です。バスタオルはおむつ替えからおくるみ、掛布団と幅広く使うことができるため何枚か用意しておくと安心です。また、混乱した状況下で子どもと離れ離れになってしまう可能性もあります。普段は自身の名前や住所をはっきりと伝える事ができる子でも、災害時にはパニックで言葉が出なくなる事もあります。必ず、子どもが身につけるものに家族の写真と連絡先を準備しましょう。

災害への備えでは、子どもの視点も取り入れることも大切です。
その際、お子さんのものを大人だけで準備したり、一方的に教えたりするだけではなく、お子さんと一緒に準備して、一緒に考えることが必要です。そうすることで、より災害時の子どもと親や養育者の安心・安全につながります。また、お子さんと一緒に避難する際、みなさんが決めている避難経路は安全でしょうか?
避難場所やそこまでの道のりなどをお子さんと一緒に確認して、実際に歩いてみましょう。災害は、親と子どもが一緒にいる時に起きるとは限りません。お子さんがよく遊びに行く場所や、普段使っている通学路などで災害が起きたときには、どこにどうやって避難すればいいか、お子さんと一緒に考えるように意識してみてくださいね。
その際、お子さんのものを大人だけで準備したり、一方的に教えたりするだけではなく、お子さんと一緒に準備して、一緒に考えることが必要です。そうすることで、より災害時の子どもと親や養育者の安心・安全につながります。また、お子さんと一緒に避難する際、みなさんが決めている避難経路は安全でしょうか?
避難場所やそこまでの道のりなどをお子さんと一緒に確認して、実際に歩いてみましょう。災害は、親と子どもが一緒にいる時に起きるとは限りません。お子さんがよく遊びに行く場所や、普段使っている通学路などで災害が起きたときには、どこにどうやって避難すればいいか、お子さんと一緒に考えるように意識してみてくださいね。