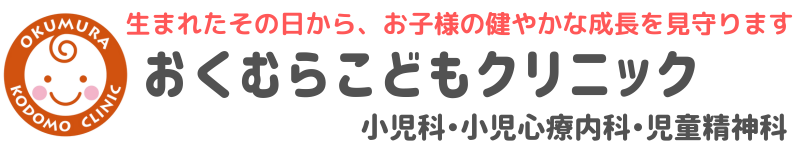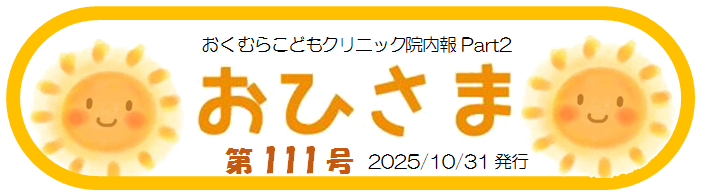おひさま 第111号~ 小児科医3?年目にして思うこと/ 知っているようで知っていない大晦日 行事~
おくむら先生のお話【小児科医3?年目にして思うこと】

不安のない子育てはありません。成長したら不安がなくなるかというと、そうでもなく、成長したらしたで、別の悩みが増えます。学童期にはいると、朝起きられない、お腹が痛い、頭が痛い、不登校、ひきこもり、オーバードーズなど色々な問題が起こります。長年小児科医をやっていると、これら全てが特別ではなく、誰にでも起こりうることで、根っこは同じではないかと思っています。前述のようなお子様は、おとなしくて、悩み事などを他人には言えない、なんなら何でこうなったのか本人もわからない、自分の意見を言えない、自己肯定感が低い、自分はダメな人間だと思っているなどといった傾向があります。このため壁にぶつかっても乗り越えられず、色々な症状がでます。これらは単なる子供の問題と思われがちですが、そうではなく、小さい頃からの親子関係、家庭環境からくる愛着の問題が大きく関わっている印象をうけます。愛着とは乳幼児期から学童期にかけて子供が親との間で築く信頼や安心感の基盤です。これがないと子供は精神的な不安定さをかかえ、自分は大切にされていないと思い、自己肯定感が低下し、私なんてどうなってもいいやと思ってしまいます。そして、学童期に不登校など色々な形で現れます。愛着って難しそうなワードですが、そうではなく、生まれた瞬間から、こどもに対して笑いかけたり、話しかけてあげたり、うなずいてあげて、子供が自分は愛されていると感じられればそれでいいのです。心配事はつきませんが、いつも不安で、眉間にしわをよせて子育てしていると、親はこどもの安全基地にはなれません。こどもがいろんなことを発信しているのに親がスマホに夢中になって子供との会話や視線の共有が減ると、親にとってじぶんの話は重要ではない、何をやっても無駄だと思ってしまいます。すると自己肯定感がさがり、投げやりになるし、他人はもちろんのこと親にも頼ることができず、ひきこもってしまいます。こうなってからだと、一旦下がってしまったものをあげるのは大変です。こどもをなんとかしようと必死になりますが、当然親さんも変わらなければ、こどもも変わりません。
心配なことはたくさんありますが、まずは目の前の我が子をみて、笑いかけて、抱きしめて、話をきいてあげてください。これだけで十分じゃないのって最近思います。
心配なことはたくさんありますが、まずは目の前の我が子をみて、笑いかけて、抱きしめて、話をきいてあげてください。これだけで十分じゃないのって最近思います。
スタッフコラム【知っているようで知ってない大晦日行事】
早いもので今年も残すところ数ヶ月となりました。今回は、日本の文化として大切にされてきた大晦日の由来・除夜の鐘・年越し蕎麦など年末行事について紹介させていただきます。
【大晦日の由来】
大晦日は年明けと共に歳神様をお迎えし、祀るための準備を行う日だとされています。(歳神様は、新年に家々を訪れて豊作や、健康をもたらす神様)そのため、家を清め飾り付けをすることは神様を迎える儀式として意味があります。
大晦日は年明けと共に歳神様をお迎えし、祀るための準備を行う日だとされています。(歳神様は、新年に家々を訪れて豊作や、健康をもたらす神様)そのため、家を清め飾り付けをすることは神様を迎える儀式として意味があります。

【門松】
門松などお正月飾りは早いところでは12月13日からですが、一般的には12月28日から飾りつけるところが多いようです。
12月29日に飾るのは二重苦で縁起が悪いとされ、30日は旧暦の大晦日で31日は新年前日で一夜飾りとも言われて避けた方がよいとされています。
門松などお正月飾りは早いところでは12月13日からですが、一般的には12月28日から飾りつけるところが多いようです。
12月29日に飾るのは二重苦で縁起が悪いとされ、30日は旧暦の大晦日で31日は新年前日で一夜飾りとも言われて避けた方がよいとされています。

【除夜の鐘】
除夜の鐘は大晦日の夜から元旦にかけて108回の鐘を鳴らす行事です。
108回→人間の煩悩の数を表しそれを浄める意味。最後の鐘を「年を越してから」つくことで新年を清らかに迎える
除夜の鐘は大晦日の夜から元旦にかけて108回の鐘を鳴らす行事です。
108回→人間の煩悩の数を表しそれを浄める意味。最後の鐘を「年を越してから」つくことで新年を清らかに迎える

【年越し蕎麦】
大晦日に欠かせない縁起物の食べ物と言えば年越し蕎麦です。なぜ大晦日に年 越し蕎麦を食べるのかというと由来には諸説あります。
・蕎麦の麺の形状が細く長いことから……長寿祈願
・蕎麦の麺は簡単に切れることから……一年の厄を断ち切る
・金銀細工師が散らばった金粉を集める縁起物として……運気上昇
大晦日に欠かせない縁起物の食べ物と言えば年越し蕎麦です。なぜ大晦日に年 越し蕎麦を食べるのかというと由来には諸説あります。
・蕎麦の麺の形状が細く長いことから……長寿祈願
・蕎麦の麺は簡単に切れることから……一年の厄を断ち切る
・金銀細工師が散らばった金粉を集める縁起物として……運気上昇
※お正月の行事は地域性が豊かで紹介させていただいた事は一例にすぎません。書かれていることと地域の習わしが違うこともあると思いますがその際は地域の習わしを大切にしてください。
1年を振り返り良いことだけではなく、悪いことも思い出し、来年に向け目標をたてると良いですね!
1年を振り返り良いことだけではなく、悪いことも思い出し、来年に向け目標をたてると良いですね!